9回目の授業で勉強すること/12月7日(月)
9回目の授業で勉強すること/12月7日(月)
1. 製本タイム。
前回の課題「学校へ行く道」の張り合わせ製本バージョンを完成させましょう。
2. 「自分ができること」棚卸し
作業がすんだ人は次作について思いを巡らせます。
最終作品の案出しです。作りたいものをはっきりさせます。
・まず、自分のこれまでの制作の履歴や習ったスキルを書き出してみましょう。こういった、ふだんは見えていない宝を確認して「自分棚卸し」をします。
・費用もどれだけの予算がとれるかを考えて、現実的な条件を書き出します。今回作れるものの姿をスケッチしてみましょう。
■今週の宿題「最終作品の企画書」と「見開きページのサンプル(原寸大)」
・A4サイズ1枚にまとめた簡単な企画書と具体的な内容ページ1見開き分を作成してプリントする。内容ページサンプルは原寸大。
次週の授業開始時提出。
※企画書に必要なもの
1作品のタイトル
2制作のコンセプト
3掲載作品の一部を添付する。
(写真やイラストの見本、小説や文章の一節、
またはラフスケッチ。1見開き文か全体のイメージイラストでも可)
09-01/コンテンツを探す|自分の能力棚卸し
これはわたしが実際に、仕事をしているときによく使う手です。頭の中がもやもやしてまとまらないときは、ただ頭の中で思いを巡らせるだけでなく、「紙とペンを使って考える」ということをしています。
企画を考えるにはいろいろな方法がありますが、べん図を使って案を出す方法をご紹介します。
・クロッキーブックかノートに、中に単語を10〜20書き入れられる大きさの円を2つ描いてみましょう。
・2つの円は円弧の一部が少し重なるようにします。
・左側の円の中をAとして、「作りたいもの」書き出します。
・右側の円をBとして、持っているものや準備しているもの、自分のスキルなどを「できること」を書き入れます。
・今回作る企画はAとBの重なり合った部分に隠れています。
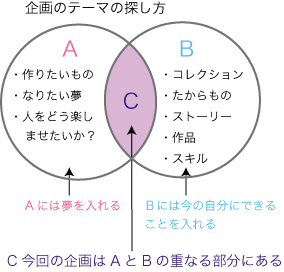
*AとBに書かれた内容を線で結んだり、続けて読み上げたりしながら、一つ一つマッチングさせて、重なり合った「今できる最高の表現」をあみだすのです。二つのワードを繋いで「具体的な単語」にしてみます。
たとえば、
・宮沢賢治が好き。宮沢賢治の詩の魅力をもっといろんな人に知ってもらいたい。詩の一つをイラストに起こして小さな絵本にする。いまだかつてないイメージの宮沢賢治本をめざす。
・将来は3DCGのクリエーターになりたい。この授業で本の作り方を覚えた。PCに依存しないエンターテイメントにあえて挑戦する。授業で作ったキャラクターを主人公にしてぱらぱらマンガを作って幼稚園児にも老人にも楽しんでもらいたい。
・自作のラノベで人々に元気を与えたい。今できている部分を短編にまとめて、文庫本の形にしてみる。
・とにかく、ITの分野で人の為になりたい。自分の能力を他人にアピールする必要がある。他の授業で作った課題も集合させて現時点の作品集を作る。
・わたしは爪がきれい。爪を見ていると心がなごむ。そんなちいさなくつろぎやときめきがあるということを人に知ってもらい、みんなにも楽しんでもらいたい。ネイルアートだけで写真集を作る。
いちばん作りたいものを一つだけ選んでください。
09-02/コンセプトを決める
テーマが決まった人はべん図を再度使って、この企画のコンセプトを作りましょう。
先ほどよりもうちょっと深い部分でべん図をおこしてみます。
Aにはもともとのアイデアを書き入れます。
Bには、自分が今回したい作業の内容を書きいれます。
重なった中央の部分が、今回の作品の特徴です。これをわかりやすい単語に置き換えてみましょう。
A:宮沢賢治の詩「雨ニモ負ケズ」
B:イラスト 旅の絵日記
C:旅を味わう「雨ニモ負ケズ」→どこにもない特徴であり、伝わりやすいワード
コンセプトということばには「ものをつくるときの方向性とアイデアを支えるキモのキーワード」という意味があります。
だれにでも理解できる、わかりやすい言葉であることが条件です。
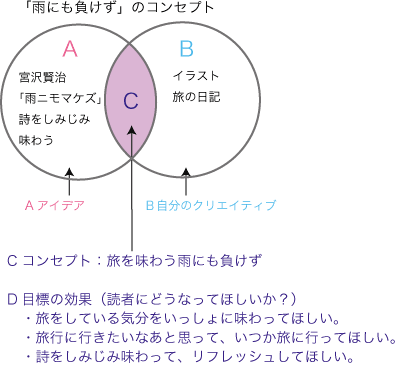
ものつくりは普通、独りで行うものでなく、必ずたくさんの人たちとのチームワークで生まれます。
実際の仕事の現場での制作では、まず最初に目的が決まります。(今回の課題ではテーマ)コンセプトは、クライアントも制作者も含んだチーム全体の「共通の問題について解決案」についての話し合いで練られるものです。
独りだけで決定するものでも、制作者側、クライアントサイドのどちらか一方の押しつけで決めるものではないです。
コンセプトは制作が進行するあいだじゅう、灯台の明かりのように、チームの標語として掲げられます。
コンセプトが適切かどうかで、チーム一人一人の意識がしゃきっと同じ方向を目指せます。
芯がぶれない、伝わりやすい仕事になるかどうかが大きく左右されますし、効率にも影響します。
今回の制作は個人プレーですが、コンセプトをはっきり持って制作に取り組みましょう。最初に計画したものを最後まで作り切れるように、自分のための「制作の核心キーワード」を一つ決めましょう。
09-03/制作スケジュールを決める
制作スケジュールを決めます。
まず、しなくてはならないことがらを書き出してみましょう。
そのことがらに優先順位をつけます。
仕事の速さには個人差があります。
自分の現在の力の範囲で、最高にいいものを作りましょう。
■今後の授業スケジュール 授業のスケジュールです。
・12月5日(月)9日(金)9回目 テーマとコンセプト決定
宿題:企画とコンセプト、1見開き分
・12月12日(月)16日(金)10回目 ページデザインの基礎
宿題:本文3見開き分
・12月19日(月)23日(金)11回目 進行チェック いろいろな構造
宿題:表紙のデザイン提出
・12月26日(月)1月6日(金)12回目 進行チェック ハードカバーの表紙作り方
宿題:本文続き分
・12月28日(水)1月13日(金)13回目 製本実習日(生徒作業日)
・1月16日 (月)20日(金)14回目 第一次発表会
・1月23日 (月)27日(金)最終プレゼンテーション
・2月1日 (水)午後7時 修正点を改善した上で、最終提出締め切り
自分の制作のスケジュールを授業の宿題スケジュールに合わせて立てます。
09-04/企画を立てる・企画書を書く
仕事の始めに、「今回の仕事はこういう考えをもとにこういう物を作ります」という考えを述べた書類を作ります。これが企画書です。
クライアントは、企画書とラフデザインから、まだできていないデザイン案の完成品のイメージや効果を予測します。
企画書には
・この仕事全体の目指す姿(企画タイトル/コンセプト)
・記事や企画の概要
・デザインの説明
・スケジュール
・予算
・価格
など、ラフデザインでは表現しきれない、データや詳細の情報を載せます。
クライアントが仕事を発注するかどうか、あるいは、どのくらいの予算が必要か、どんな人たちが制作に関わるのかを決定する、重要な役割を果たします。
また、新たに企画を売リこむ場合もあります。新しいスポンサーや顧客を獲得するための営業ツールとなります。
制作時にはチームに加わるいろいろなスタッフにも仕事の内容や規模を伝える資料として配られ、チーム全体が最初の目的を外すことなく、完成というゴールを目指すための目安となります。
■企画書を書いてみよう
今回の課題の企画書を書いてみましょう。
A4企画書例
*企画書に入れる内容
1タイトル
2キャッチフレーズ(この企画を一言で表すと。"コンセプト")
3説明。まず、どういうものかをわかりやすく。
何が書いてあるか?(what)
誰に向けたものか?(who)
いつ見てもらう?(when)
どんな場面で見てもらう?どこで売る?(where)
どのように使用する?(how)
なぜ必要か?(why)
そして、期待する効果をあげる。
「その本をみて、どうなってほしいか?」が盛り込まれるとよい。
以上のことを箇条書きにしてから文章にまとめるとわかりやすくなる。
文章はわかりやすく。小学生にもわかるくらいシンプルで簡単なことばを使う。
4主な内容案
載せる記事の内容の一部を見せたり、ストーリーのあらすじを紹介するなど。
5仕様
判型:大きさ 組方向 綴じ方 ページ数
09-05/ストーリーボード&絵コンテ・台割り
企画の方針が決まったら、全体のページの流れを考えます。映画ではストーリーボード、CM制作だと絵コンテと呼ばれるスケッチを制作しますね。
絵本や雑誌のビジュアルは動画ではありませんが、「めくる」という動作を介して「時間」「タイミング」が大きく関わるメディアです。
本の制作でも全体の流れを見通す計画を立てる段階があります。この計画書は「台割り」と呼ばれています。台割りを作って全体の流れを設計してみましょう。
描き方は決まっていませんが下に用紙をアップロードしました。お役立てください。
台割り用紙ダウンロード
09-06/ダミーを作る
台割りで全体の流れを決めたら、立体物で確認してみましょう。
A4の白紙を4つに切ってさらに2つ折りにします。ページ数分重ねて真ん中の折り線を輪ゴムで止めます。ミニチュアの本ができました。
台割のページ内容を鉛筆でこのミニ本に1ページ1ページ書き入れていきます。ここに書き入れる絵や情報は、あとで書き換えるかもしれませんので、ごく簡単でかまいません。こうした見本のことを「ダミー」とよんでいます。
ダミーができたら、何べんもめくって、ページの順番とお話が伝わるテンポを確認しましょう。もしも改善したほうがいいなあと感じたら、あらゆる可能性をこの段階でトライしてみます。
09-07/張り合わせ製本工程1:本文を折る(再)
まず、紙を折る工程からはじめます。
今回は印刷のしてある面を内側に、センタートンボを目安にきっちり折ります。
センタートンボの見分けがつかない人は、あらかじめ、トンボの位置に針で穴をあけておくと、裏側からでも探しやすいです。
厚い紙の場合は折り目に沿って、カッターの歯の裏で傷をつけておくと降りやすくなります。
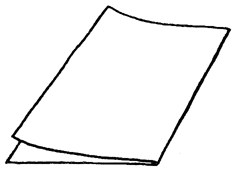
あらかじめ、ページの下を裁断線で切っておくと、紙を揃えやすいです。
09-08/張り合わせ製本工程2:貼り合わせ
トンボを目安に、背側をよく揃えます。
両端、または反対側をクリップでとめ、1センチ幅くらいにボンドを塗ります。
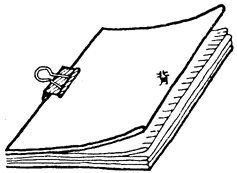
紙は水分を含むと伸びます。これがしわの原因になりますので、はった後はしっかりプレスして(本などにはさんで、自分の体重をかけるとよい)乾燥します。
※のりを塗りすぎると紙の内面に水分が通り、プリントのインクが溶けることがあります。
のどの部分に色面がある人は、折った時点で、のどの部分に薄いあて紙(雑誌の切れ端など)を入れておくとよいでしょう。
乾いたら今度は小口側をはります。
裏と裏どおしを合わせ、1センチの幅に糊をぬり、張り合わせます。
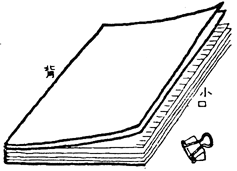
1枚おきです。間違えないように!
09-09/張り合わせ製本工程3:裁断(再)
定規で本を強く押さえ、カッターを当てます。1枚づつ切るつもりで、カッターを引きます。
カッターは垂直に。押さえる方は力を入れますが、カッターはあくまで軽く引いています。
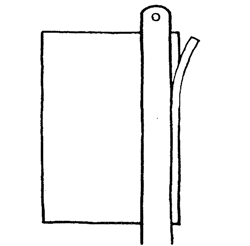
※カッターの刃は新しくしておきます。1辺につき1回、折るくらいの感じです。
※ページが乾ききっていないと失敗のもとになります。あせらず、じっくり乾かしましょう。
09-10/張り合わせ製本工程4:表紙を付ける
表紙の紙を切ります。
高さは出来上がった本の中身に合わせます。
・本文+前後の見返しの厚さを測り背の厚さにします
・裁断したあとの本文を採寸します 左右と天地に1~2mm余裕を持たせた寸法を表紙の大きさに決めます
・小口側を5cm~10cm、少し多めに折り返し部分を持たせて内側に織り込むようにすると丈夫なカバーになり、見栄えも立派です。
※↑今回は折り返し部分を作りません。表紙も本文と同じ大きさでカットしてかまいません。
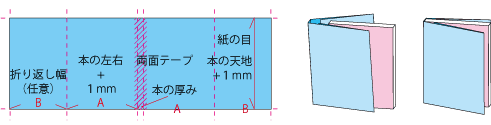
背の部分に木工ボンドを塗るか、両面テープで本体とカバーを貼り合わせます。