8回目の授業「紙の取り扱いについて」
8回目の授業「紙の取り扱いについて」
- 紙の目
- ・本を作成する場合、紙を使用する向きは外してはならない条件です。
・紙の繊維の流れを「紙の目」と呼んでいます。
・紙の目が本の背と平行になるように気をつけて、版下を設計してみましょう。
今週の宿題1
いよいよ本格的な製本のパートに入ります。
いきなり、新しいテーマに取り組む前に、前作のぱたぱた製本を「絵本とじ製本」用に設計しなおして、製本の練習をします。
本に必要なパーツの版下を設計して、画像を配置し、出力してみてください。
次週はそれらのパーツを実際に組み立ててみます。
宿題2
さて、この授業の最終作品は「本」です。
テーマもページ数も大きさも自由です。本のテーマを決めてください。
ただし、コンテンツは自作の物であること。友達や知り合いとの共作はかまいません。
デジキャン8回目に提出フォルダーを設けました。
企画を簡単にまとめて送信してください。
※締め切り:12月4日(日)
次週持ちもの
・出力紙
・カッター
・定規
・カッターマット
・製本用のクリップ2個
・木工用ボンド
・ボンド用皿
・ボンド用筆
08-02/製本のキモ「紙の目」
紙には『目』があります。
・紙を造るとき、大きなベルトコンベアに乗せて、繊維を流し込み、水分を抜いて乾燥させるという工程があります。
・ベルトコンベアの上を通った紙は大きなローラーに巻き付けられ、カットされて売られます。
・水に浮かんだ紙の繊維ががローラーにまき付けられるまでの間に、繊維の方向がベルトコンベアの進行方向に対して平行に並びます。これが「紙の目」です。
・紙は湿気を帯びると伸びます。このとき、「紙の目」にそって丸まろうとする性質があります。
・また、「紙の目と垂直方向には湾曲しにくい」という性質もあります。
・厚い紙や、薄い紙でも束になった場合、その性質が強く現れます。
・本やパンフレットにした場合、綴じる辺と平行に紙の目を使うと、スムーズに開きやすく、読みやすい書物になります。
・紙の目を閉じる辺に対して垂直に使うことを逆目(さかめ)といいます。
・紙を逆目で使った本は、湿気を含むとページが本の背と垂直方向に丸まり、開きにくい本になります。何度も開いたりに壊れやすくくなります。
■本の制作には、背と水平に「紙の目」が通るように紙を使います。
・カットされて店頭に並んだ紙や、出力紙としてパックにされた紙の中には、実はいろいろな目の紙が混ざっています。
・手製本では、あらかじめ紙の目をテストし、また、大きな紙をカットして使う場合には、わざわざ「紙の目が本の背と平行になるように」注文します。
※本の背と平行して紙の目が通った状態を「縦目(T目)」といいます。
・出力ペーパーにも「紙の目」はあります。ただし、あまり、目の性質が強いと、熱によって丸まったりして、詰まりやトラブルの原因になります。普通の書籍用紙よりも平滑に作られています。
・A3のペーパーなど大きい紙は、長方形の横長の方向に進むようにセットされることがほとんどなので、紙は「長い辺にそって紙の目が並ぶ」「横目」で作られていることが多いのです。
*課題を出力する際に、使う用紙の紙の目を確かめてから、使用する用紙の紙の目に合わせて版下を作成しましょう。
08-03/紙の目を考えて版下を作る
絵本のように、紙を二つ折りにして、糊で繋いで製本する方法を体験してみましょう。前回の課題のデータを、作り直してみます。
まず版下を作成します。
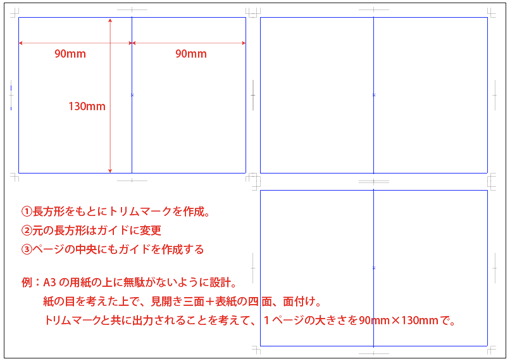
ポイントは
1 費用が安くすむように、出力する紙に合わせて、ページの大きさを決める。
2 紙の目を考えて面付けをする。
この2点です。
1枚の紙に何面か版下を組み合わせることを「面付け」と呼んでいます。
版下が引けたら、写真を配置してみましょう。
版下のベースをいきなりしようしないで、ベースはテンプレートとして保存しておいて、別名で保存して複製していきます。
この例は1ページを90×130mmで作成しています。写真の塗り足し分が足りない部分は、写真をトリミングし直すとよいでしょう。
04-04/表紙を設計する
中身を張り合わせ、裁断したら、本文に合わせてカバーの設計をします。
サイズが必要な場所は3カ所です。
1 本文の天地(130mm)
2 本文の幅 (90mm)
3 本文の厚み(2mm)
測ったサイズに従って、表紙を製図していきます。
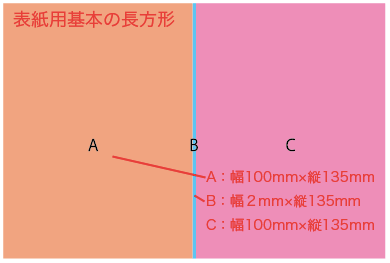
「オプション」「変形」「移動」コマンドを使用して、基本の長方形をぴったりのサイズですきまなく並べます。
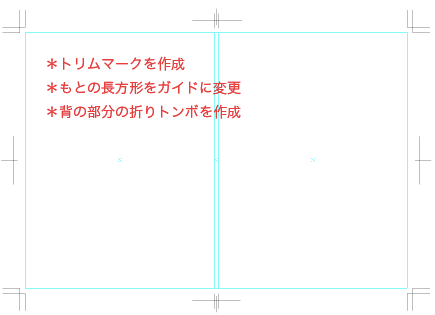
並べた長方形からトリムマークを作成し、もとの長方形からガイドを作成し、背の部分の折りトンボを作成しておきます。
表紙の写真を配置するときは、左右を間違えないように注意しましょう。